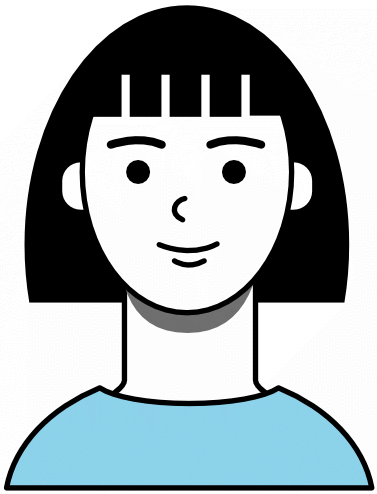top of page


聖徳太子の生誕地「橘寺」@奈良
奈良県明日香村にある「橘寺」。聖徳太子の生誕地と伝わり、聖徳太子が建立したとされる七大寺の一つです。 聖徳太子建立七大寺とは、法隆寺、広隆寺、法起寺、四天王寺、中宮寺、橘寺、葛木寺。 (葛木寺は唯一所在が確認されていません) 本堂...
2022年5月26日読了時間: 3分


聖徳太子の等身像・救世観音像「法隆寺・夢殿」@奈良
夢殿(国宝) 奈良県生駒郡斑鳩町にある「法隆寺・夢殿」。 法隆寺の境内は西院伽藍と東院伽藍に大きく分かれ、夢殿は東院伽藍の本堂になります。 聖徳太子が、推古天皇9年(601)に斑鳩宮(太子の住居)を造営。夢殿は斑鳩宮の跡地にあたり、朝廷の信任厚かった高僧・行信が宮跡の荒廃ぶ...
2021年9月8日読了時間: 4分


聖徳太子が創建、世界最古の木造建築群「法隆寺」@奈良
奈良県生駒郡斑鳩町にある「法隆寺」。 推古天皇9年(601)に、聖徳太子が斑鳩宮を造営。ほどなく、ここに亡き父・用明天皇のため寺の造立を発願され、推古15年(607)に創建されたのが法隆寺です。 「日本書紀」によると天智9年(670)に、一屋余す事無く焼失したと記されていま...
2021年9月1日読了時間: 4分


聖徳太子が創建「法起寺」@奈良
奈良県生駒郡斑鳩町にある「法起寺(ほうきじ)」。 推古14年(606)に聖徳太子が法華経を講説されたという岡本宮を、寺に改めるよう太子の子・山背大兄王(やましろのおおえのおう)に遺言したことにより、推古30年(622)に建立されたとされます。...
2021年8月27日読了時間: 2分


聖徳太子の子・山背大兄王が創建「法輪寺」@奈良
奈良県生駒郡斑鳩町にある「法輪寺(ほうりんじ)」。 法隆寺がある「斑鳩(いかるが)の里」の北方に位置し、飛鳥時代の仏像と飛鳥様式の三重塔で知られています。 推古30年(622)、聖徳太子の子・山背大兄王(やましろのおおえのおう)によって、太子の病気平癒を願って建立されたと伝...
2021年8月23日読了時間: 3分


唐から来日した鑑真が創建「唐招提寺」@奈良
奈良県奈良市にある「唐招提寺(とうしょうだいじ)」。 南都六宗の一つである律宗の総本山です。 多くの苦難の末に来日された唐の高僧・鑑真和上によって、天平宝字3年(759)に戒律を学ぶ人々の修行道場として創建されました。 鑑真和上は日本に着いてから最初の5年間は東大寺で過ごし...
2021年8月16日読了時間: 3分


黒川紀章が設計「入江泰吉記念 奈良市写真美術館」@奈良
奈良県奈良市にある「入江泰吉記念 奈良市写真美術館」。 写真家・入江泰吉の全作品(約8万点)を所蔵する、西日本最初の写真専門美術館です。 入江泰吉の没後、全作品を奈良市に寄贈されたのを機に、建築家・黒川紀章による設計で、1992年4月に開館されました。 入江泰吉(いりえ...
2021年8月13日読了時間: 2分


安藤忠雄が設計「市立五條文化博物館」@奈良
奈良県五條市にある「市立五條文化博物館」。 地域の歴史や文化遺産を収蔵・展示・研究する施設として、建築家・安藤忠雄氏による設計で、平成7年(1995)4月に開館されました。 安藤忠雄(あんどう ただお) 大阪生まれ。1941年〜...
2021年8月12日読了時間: 1分


吉田五十八が設計「大和文華館」@奈良
奈良県奈良市にある「大和文華館」。 昭和35年(1960)、近鉄の創立50周年行事の一環として開館されました。 昭和を代表する建築家・吉田五十八による設計。コンクリートで日本的空間を目指した、吉田五十八の代表作のひとつ。 吉田五十八(よしだ いそや)...
2021年8月11日読了時間: 1分


はだか地蔵尊の衣替え「伝香寺」@奈良
奈良県奈良市にある「伝香寺(でんこうじ)」。 伝香寺は戦国時代の大名、筒井順慶の菩提所として建立されました。 筒井順慶(つつい じゅんけい) 天文18年(1549)~天正12年(1584) 父の死により2歳で家督を継ぎ、筒井城主となる。永禄2年(1559)松永久秀に筒井城を...
2021年7月21日読了時間: 2分


あじさい寺として有名「矢田寺」@奈良
奈良県大和郡山市にある「矢田寺(やたでら)」。 別名「あじさい寺」とも呼ばれ、6月から7月のシーズンを迎えると境内にある約60種10,000株のあじさいの花が咲き乱れます。 寺伝によると、大海人皇子(後の天武天皇)が壬申の乱の戦勝祈願のため矢田山に登られ、即位後の白鳳4年(...
2021年7月15日読了時間: 1分


アフロヘアの五劫思惟阿弥陀仏「五劫院」@奈良
奈良県奈良市にある「五劫院(ごこういん)」。 東大寺の末寺で、東大寺境内外、正倉院より北へ徒歩10分ほど、静かな住宅街にある小さな寺院です。 五劫院縁起によると、重源上人が宋に渡られ、浄土教高祖・善導大師の御作、五劫思惟阿弥陀佛を請来され、東大寺北門に一堂を建立し御本尊とし...
2021年6月8日読了時間: 2分


奈良の大仏「東大寺・大仏殿」@奈良
奈良県奈良市にある「東大寺・大仏殿」。 東大寺の御本尊、盧舎那仏(るしゃなぶつ)坐像(通称=奈良の大仏)が安置されています。 盧舎那仏坐像は、聖武天皇の発願により天平17年(745)から制作が開始され、天平勝宝4年(752)に開眼供養会が行われました。...
2021年6月7日読了時間: 2分


奈良時代の遺構、国宝の「東大寺・転害門」@奈良
奈良県奈良市にある「東大寺・転害門(てがいもん)」。 東大寺境内の西北側にあり、762年の建立とされ、門の高さは基壇を除いて10m強。 三間一戸八脚門の形式をもつ堂々とした門で、国宝に指定されています。 奈良時代に東大寺が創建された当初の数少ない遺構で、天平時代の八脚門は法...
2021年6月6日読了時間: 1分


年に1日だけ開扉される「東大寺・開山堂」@奈良
奈良県奈良市にある「東大寺・開山堂」。 開山堂(国宝)は、普段非公開なので分かりづらい場所ですが、東大寺二月堂の下、四月堂の北側白壁の囲みの中にあります。 内陣中央に八角造の厨子がすえられ、秘仏・良弁(ろうべん)僧正坐像(国宝)が安置されており、年に1日、12月16日(良弁...
2021年6月5日読了時間: 2分


年に2日だけ開扉される「東大寺・俊乗堂」@奈良
奈良県奈良市にある「東大寺・俊乗堂(しゅんじょうどう)」。 普段は非公開ですが、年に2日、7月5日(俊乗忌)、12月16日(良弁忌)のみ開扉されます。堂の中央には秘仏・重源(ちょうげん)上人坐像が安置されています。 重源上人坐像は、重源の菩提を弔うために、弟子等が造立したと...
2021年6月4日読了時間: 2分


運慶が70日で完成させた仁王像「東大寺・南大門」@奈良
奈良県奈良市にある「東大寺・南大門」。 大仏殿へ向かう参道の途中にあり、高さ25.46mの日本最大の山門です。 天平創建時の門は平安時代の応和2年(962)に大風で倒壊。現在の門は鎌倉時代の正治元年(1199)に東大寺中興の祖・重源上人(ちょうげんしょうにん)が再建したもの...
2021年6月3日読了時間: 1分


興福寺の仏頭が本尊「山田寺跡」@奈良
奈良県桜井市にある「山田寺跡」。 現在、興福寺 国宝館で安置されている国宝・銅造仏頭は、今は頭部しか残っていませんが、かつては飛鳥山田寺の講堂本尊・丈六薬師如来像でした。その山田寺の跡地。 山田寺は、蘇我氏の一族である蘇我倉山田石川麻呂(そがのくらのやまだのいしかわまろ)の...
2021年6月2日読了時間: 2分


国宝仏像の所有数が日本一「興福寺・国宝館」@奈良
奈良県奈良市にある「興福寺」。 「古都奈良の文化財」として、東大寺や春日大社などと共に世界遺産に登録されています。 興福寺は、国宝の仏像を日本一多く所有している寺院です。 「彫刻」カテゴリーで国宝指定されている作品は全国で全136件。その中で興福寺所有の仏像は18件で、全国...
2021年6月1日読了時間: 2分


運慶の父康慶の傑作!不空羂索観音「興福寺・南円堂」@奈良
奈良県奈良市にある「興福寺」。 興福寺は南都七大寺の一つで、法相宗の大本山です。 興福寺の南円堂(重要文化財)は、弘仁4年(813)藤原冬嗣(ふゆつぐ)が、父の内麻呂の冥福を祈って建立されました。 現在の建物は、江戸時代中期の寛政元年(1789)に再建されたものです。...
2021年5月31日読了時間: 2分
bottom of page