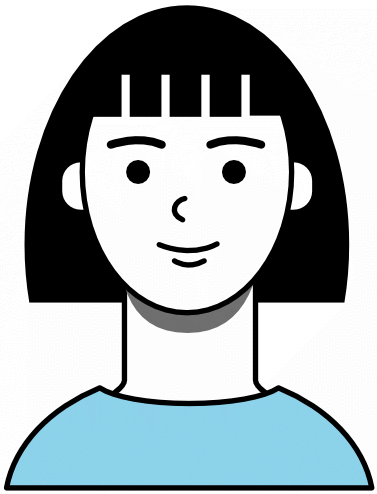top of page


巴御前の終焉の地「巴塚の松」@富山
富山県南砺市にある、巴御前の終焉の地と伝えられている「巴塚の松」。 樹齢750年を超える一本松です。 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」の影響で、少しだけ話題になっているようです。 巴御前とは、平安時代末期に活躍した木曽義仲の妾で、かつ義仲に仕えた女武者。...
2022年5月20日読了時間: 2分


はだか地蔵尊の衣替え「伝香寺」@奈良
奈良県奈良市にある「伝香寺(でんこうじ)」。 伝香寺は戦国時代の大名、筒井順慶の菩提所として建立されました。 筒井順慶(つつい じゅんけい) 天文18年(1549)~天正12年(1584) 父の死により2歳で家督を継ぎ、筒井城主となる。永禄2年(1559)松永久秀に筒井城を...
2021年7月21日読了時間: 2分


京の大仏・丈六釈迦如来「戒光寺」@京都
京都市東山区にある「戒光寺(かいこうじ)」。 泉涌寺の塔頭のひとつで、泉涌寺の境内にあります。 鎌倉時代の安貞2年(1228)、南宋から帰朝した浄業曇照(じょうぎょうどんしょう)が大宮八条の東堀川の西に戒光寺を創建。丈六の釈迦如来立像を本尊として迎え、後堀河天皇の勅願所とな...
2021年7月8日読了時間: 2分


運慶作の国宝仏が5躯も「願成就院」@静岡
静岡県伊豆の国市にある「願成就院(がんじょうじゅいん)」。 鎌倉時代初頭の文治5年(1189)に、北条政子の父親で鎌倉幕府初代執権であった北条時政が、娘婿の源頼朝の奥州藤原氏征討の戦勝祈願のため建立されました。 願成就院には、文治2年(1186)、運慶が30代の時に造った阿...
2021年6月28日読了時間: 2分


子授けの観音様「石道寺」@滋賀
滋賀県長浜市にある「石道寺(しゃくどうじ)」。 神亀3年(726)延法上人よって開かれ、行基菩薩によって境内が整備されたのが始まりと伝えられています。 その後、延暦23年(804)に伝教大師最澄が十一面観音像、脇仏持国天像、多聞天像を自ら彫り、再興したとされています。...
2021年6月25日読了時間: 1分


地蔵菩薩坐像が必見「瑞伝寺」@福井
福井県小浜市にある「瑞伝寺(ずいでんじ)」。 瑞伝寺の開創については不詳ですが、当寺に伝わる「瑞伝寺本尊縁起」によれば、鎌倉時代の承元3年(1209)に、若狭国守護・津々見忠季(つつみただすえ)の家臣・清原是定の建立とされます。...
2021年6月24日読了時間: 2分


重文の薬師如来坐像「若狭国分寺」@福井
福井県小浜市にある「若狭国分寺」。 天平13年(741)に聖武天皇の詔で、奈良に東大寺、諸国に国分寺が建てられました。若狭国分寺もその一つで、東大寺より少し遅れて奈良時代後半8世紀中頃に創建されました。 10世紀中頃まで存在していましたが火災で焼失。その後、鎌倉時代に再建さ...
2021年6月20日読了時間: 1分


アフロヘアの五劫思惟阿弥陀仏「五劫院」@奈良
奈良県奈良市にある「五劫院(ごこういん)」。 東大寺の末寺で、東大寺境内外、正倉院より北へ徒歩10分ほど、静かな住宅街にある小さな寺院です。 五劫院縁起によると、重源上人が宋に渡られ、浄土教高祖・善導大師の御作、五劫思惟阿弥陀佛を請来され、東大寺北門に一堂を建立し御本尊とし...
2021年6月8日読了時間: 2分


年に2日だけ開扉される「東大寺・俊乗堂」@奈良
奈良県奈良市にある「東大寺・俊乗堂(しゅんじょうどう)」。 普段は非公開ですが、年に2日、7月5日(俊乗忌)、12月16日(良弁忌)のみ開扉されます。堂の中央には秘仏・重源(ちょうげん)上人坐像が安置されています。 重源上人坐像は、重源の菩提を弔うために、弟子等が造立したと...
2021年6月4日読了時間: 2分


運慶が70日で完成させた仁王像「東大寺・南大門」@奈良
奈良県奈良市にある「東大寺・南大門」。 大仏殿へ向かう参道の途中にあり、高さ25.46mの日本最大の山門です。 天平創建時の門は平安時代の応和2年(962)に大風で倒壊。現在の門は鎌倉時代の正治元年(1199)に東大寺中興の祖・重源上人(ちょうげんしょうにん)が再建したもの...
2021年6月3日読了時間: 1分


国宝仏像の所有数が日本一「興福寺・国宝館」@奈良
奈良県奈良市にある「興福寺」。 「古都奈良の文化財」として、東大寺や春日大社などと共に世界遺産に登録されています。 興福寺は、国宝の仏像を日本一多く所有している寺院です。 「彫刻」カテゴリーで国宝指定されている作品は全国で全136件。その中で興福寺所有の仏像は18件で、全国...
2021年6月1日読了時間: 2分


運慶の父康慶の傑作!不空羂索観音「興福寺・南円堂」@奈良
奈良県奈良市にある「興福寺」。 興福寺は南都七大寺の一つで、法相宗の大本山です。 興福寺の南円堂(重要文化財)は、弘仁4年(813)藤原冬嗣(ふゆつぐ)が、父の内麻呂の冥福を祈って建立されました。 現在の建物は、江戸時代中期の寛政元年(1789)に再建されたものです。...
2021年5月31日読了時間: 2分


運慶の傑作!無著・世親菩薩立像「興福寺・北円堂」@奈良
奈良県奈良市にある「興福寺」。 興福寺は南都七大寺の一つで、法相宗の大本山です。藤原氏の祖・藤原鎌足とその子・藤原不比等ゆかりの寺院で、藤原氏の氏寺です。 興福寺の北円堂(国宝)は、藤原不比等の1周忌にあたる養老5年(721)8月に、元正天皇の命で長屋王によって建立されまし...
2021年5月30日読了時間: 2分


大化改新の談合の地「談山神社」@奈良
奈良県桜井市にある「談山(たんざん)神社」。 中臣鎌足(後の藤原鎌足)と中大兄皇子(後の天智天皇)が、大化元年(645)の5月に多武峰(とうのみね)の山中に登って「大化改新」の談合を行い、後にこの山を「談い山(かたらいやま)」「談所ヶ森」と呼び、それが談山神社の名前の由来と...
2021年5月24日読了時間: 3分


東洋のミューズ!伎芸天を祀る「秋篠寺」@奈良
奈良市にある秋篠寺(あきしのでら)は、第49代天皇・光仁(こうにん)天皇の勅願により奈良時代の僧・善珠(ぜんじゅ)が宝亀7年(776年)に創建したとされています。 光仁天皇といえば、壬申の乱以降、百年ほど続いた天武天皇系の皇統が天智天皇系へ移った(戻った)天皇としても知られ...
2021年4月13日読了時間: 3分


33年に一度のご開帳「蓮華寺」@富山
■ 御本尊の御開帳は33年に一度 富山県高岡市にある、蓮華寺(れんげじ)。 秘仏・御本尊のご開帳は33年に一度。2017年4月23日に行われました。 次回は2050年…。 寛喜三年(1231年)、鎌倉・大楽寺の観行律師が源頼朝公の守本尊・十一面観世音像を始め、多くの宝物を携...
2017年4月27日読了時間: 1分


行基菩薩が彫られた本尊を有する「十三寺」@富山
■ 元宿場町にひっそりとあるお寺 富山県入善町にある、十三寺(じゅうそうじ)。 旧北陸道上街道に面した元宿場町舟見にあります。 十三寺の創建は不詳ですが、伝承によると天平年間(729~749年)に、行基菩薩が巡錫で当地を訪れた際、紫雲のたなびくのを御覧になり、そこにそびえる...
2017年4月26日読了時間: 2分


運慶のデビュー作を安置「円成寺」@奈良
■ 運慶のデビュー作の大日如来座像。 奈良県奈良市にある円成寺(えんじょうじ)。 奈良市と言っても、近鉄奈良駅から車で25分くらい離れていて山奥です。 天平勝宝8年(756)聖武上皇・孝謙天皇の勅願で、鑑真和上の弟子、唐僧虚滝和尚の開山であるとされています。...
2017年4月10日読了時間: 1分


美しい十一面観音「海龍王寺」@奈良
■ 旅行・留学安全祈願の寺院 奈良県奈良市にある海龍王寺。 天平3(731)年、遣唐使として中国に渡っていた初代住持の玄昉が、一切経と新しい仏法とを無事に我が国にもたらすことを願い、光明皇后によって創建。 山門 山門をくぐって細い道を進みます。 本堂(江戸時代)...
2017年4月9日読了時間: 1分
bottom of page