日本の夜を守る「日御碕神社」@島根
- Asami
- 2021年5月10日
- 読了時間: 2分

島根県出雲市にある「日御碕(ひのみさき)神社」。
「出雲国風土記」に「美佐伎社」と記される歴史ある神社です。
下の宮「日沈宮(ひしずみのみや)」と上の宮「神の宮」の上下二社からなり、両本社を総称して「日御碕神社」と呼ばれます。
日沈宮の御祭神は天照大御神(アマテラスオオミカミ)、神の宮の御祭神は須佐之男命(スサノヲノミコト)が祀られています。
伊勢神宮が「日の本の昼を守る」のに対し、日御碕神社は「日の本の夜を守る」といわれています。
日が昇る東の伊勢神宮、日が沈む西の日御碕神社。


日沈宮
神代の昔、日御碕神社から程近い海岸「清江の浜」の「経島」に天照大御神が降臨し、「吾はこれ日ノ神なり。此処に鎮りて天下の人民を恵まん。汝速かに吾を祀れ」との神勅があり、これに喜んだ天之葺根命(アメノフキネノミコト)が直ちに島上に大御神を祀った、と伝わります。
天之葺根命は、須佐之男命の五世の孫で、大国主神の父とされています。
のちに第62代天皇・村上天皇(926年〜967年)は、「日御碕は夕日をはなむけ祀る霊地一」として崇敬され、現社地に宮を造営して遷座されました。

神の宮
出雲の国造りをされて根の国(黄泉国)に渡った須佐之男命が「吾が神魂はこの柏葉の止まる所に住まん」と柏の葉を投げて占ったところ、柏葉は風に舞いこの神社背後の「隠ヶ丘」に止まりました。
その後、天之葺根命がこの地に須佐之男命を奉斎したのが「神の宮」です。



廻廊

現在の建物は、徳川家光の命により、寛永14年(1637)藩主京極忠高が着手し、同21年(1644)藩主松平直政によって完成しました。桃山時代の面影を残す貴重な神社建築として、14棟一括重要文化財に指定されてています

海が近いので、境内にいても潮の香りがしました。

天照大神が日御碕神社に祀られる以前に鎮座されていたという経島(ふみしま)。
その形状が「経典」を積み重ねたように見えるため、その名がついたと伝えられています。
経島は日御碕神社の神域として神職以外の一般の立入りは禁止されており、年に一度8月7日の例祭の時のみ、宮司だけがその島に舟で渡ることができます。
<日御碕神社>
【住所】島根県出雲市大社町日御碕455
【電話】0853-54-5261
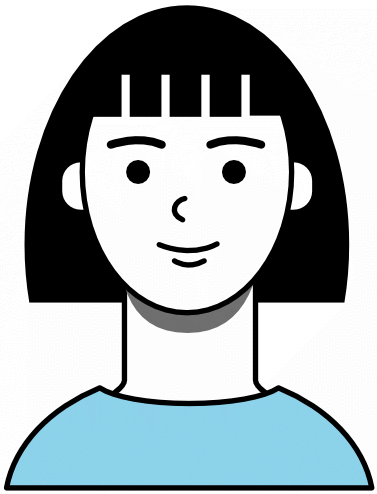
Comentários