
夢殿(国宝)
奈良県生駒郡斑鳩町にある「法隆寺・夢殿」。
法隆寺の境内は西院伽藍と東院伽藍に大きく分かれ、夢殿は東院伽藍の本堂になります。
聖徳太子が、推古天皇9年(601)に斑鳩宮(太子の住居)を造営。夢殿は斑鳩宮の跡地にあたり、朝廷の信任厚かった高僧・行信が宮跡の荒廃ぶりを嘆いて太子供養の伽藍の建立を発願し、天平11年(739年)に創建したとされています。
堂内には聖徳太子の等身像とされる秘仏・救世観音像が安置されています。
通常非公開ですが、春季と秋季の一定期間のみ特別公開されます。
<夢殿本尊 特別開帳>
春季:4月11日〜5月18日、秋季:10月22日〜11月22日

救世観音像(国宝)
飛鳥時代作、楠の一木造り、像高178.8cm
長い間、法隆寺の僧侶さえ拝むことが許されなかった秘仏で、法隆寺の仏像の中で最も謎に満ちた仏様です。
「聖徳太子伝私記」によると、この像を彫った仏師は、仏の完成後まもなく原因不明の死を遂げたとされます。鎌倉時代には、これを模刻しようとした仏師が像の完成を見ることなく亡くなったという話もあるそうです。
また、救世観音像の頭には大きな釘で光背が直接打ち付けられており、太子の怨霊を封じ込めるために意図的になされた行為といわれています。仏像の頭に釘を打つ、なんてことは普通あり得ませんので、ますますミステリーです。
それらの逸話もあってか、白布に包まれて長年封印され、僧侶たちは封印を解けば直ちに神罰が下り、地震で全寺が倒壊するという迷信を信じていました。
そんな折、明治17年(1884)に東洋美術史家のアメリカ人、アーネスト・フェノロサと岡倉天心が調査のため法隆寺を訪れ、観音像の開帳を説得します。僧侶たちは聖徳太子の怒りを恐れて封印を解くことを頑なに拒み、長く硬直状態が続きますが、最後にはフェノロサの要求が聞き入れられ、開帳されることになりました。
その時のフェノロサの興奮は「東亜美術史綱」に以下のように記されています。
『・・・二百年間用ひざりし鍵が錆びたる鎖鑰内に鳴りたるときの余の快感は今に於いて忘れ難し。厨子の内には木綿を以て鄭重に巻きたる高き物顕はれ、其の上に幾世の塵埃堆積したり。木綿を取り除くこと容易に非ず。飛散する塵埃に窒息する危険を冒しつつ、凡そ500ヤードの木綿を取り除きたりと思ふとき、最終の包皮落下し、此の驚嘆すべき無二の彫像は忽ち吾人の眼前に現はれたり。』
特別開帳の拝観は、夢殿の外から金網越しに、厨子の中にいらっしゃる救世観音像を拝むことになるので、ハッキリと全体像を捉えることはできません。夢殿の中は薄暗く、その中で佇むお姿を凝視しようとしつつも、でもあまり直視してはいけない感じもして、畏怖の念が湧いてきます。闇の中でうっすらと笑みを浮かべた表情はどこか不気味で、仏様に向かって不謹慎かもしれませんが、ゾッとする感じがしました。超個人的感想。

舎利殿(重要文化財)
聖徳太子が2才の春に東に向って合掌され、その掌中から出現したという舎利(釈迦の遺骨)を安置する建物。
毎年1月1日から三日間「舎利講」という法要が行われ、舎利が御開帳されます。


大宝蔵院
法隆寺に伝来する数々の名宝が安置されています。百済観音像や夢違観音像、橘夫人念持仏と伝えられる阿弥陀三尊像など見どころ多数です。

百済観音像(国宝)
飛鳥時代作、楠の一木造り、像高209.4cm
昭和初期まで金堂内に安置されていましたが、現在は大宝蔵院の百済観音堂に安置されています。飛鳥時代を代表する傑作の一つ。
八頭身の長身、美しい体躯が特徴で、横から見るとその美しさがより分かります。

夢違観音像(国宝)
白鳳時代作
この観音様に祈ると悪い夢を良い夢に変えてくださる、という信仰から「夢違観音」と呼ばれています。白鳳時代の代表作の一つ。

伝橘夫人念持仏 阿弥陀三尊像(国宝)
白鳳時代作、金銅仏
もとは金堂内に安置されていましたが、現在は大宝蔵院に安置されています。厨子入りの精巧な金銅阿弥陀三尊像で、彫刻、絵画、工芸が一体となった傑作。
橘三千代(たちばなのみちよ)
天武天皇から元正天皇の5代に仕えた女官。
藤原不比等の夫人で、光明皇后の母。光明皇后は聖武天皇の皇后。
光明皇后は厚く仏教を信仰し、奈良時代以後の聖徳太子信仰に大きく影響を与えた。

上御堂(重要文化財)
天武天皇の皇子である舎人親王の発願によって建立されますが、永祚元年(989)に倒壊し、現在の建物は鎌倉時代に再建されたものです。
堂内には平安時代の釈迦三尊像(国宝)と室町時代の四天王像(重要文化財)が安置されています。

釈迦三尊像(国宝)
釈迦三尊像(釈迦如来・文殊菩薩・普賢菩薩)。
通常非公開ですが、毎年11月1日~3日に特別開扉されています。
数年前に、上御堂の特別開扉に訪れたことがあります。法隆寺は飛鳥時代のお寺、というイメージが強いので、こちらの平安仏が新しく感じる不思議。十分古いものなんですけどね。

パンフレット



見応え十分、敷地も広い法隆寺。特別開扉に合わせて行くなら、行列も見越して時間に余裕を持って行くべし。慌ててまわるのは勿体無いです。
近くには中宮寺や法輪寺、法起寺などもあるので、斑鳩の里だけで1日かけて参拝するといいかもです。
<法隆寺>
【住所】奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1
【電話】0745-75-2555
【時間】8:00〜17:00
【拝観料】大人1,500円、小学生750円
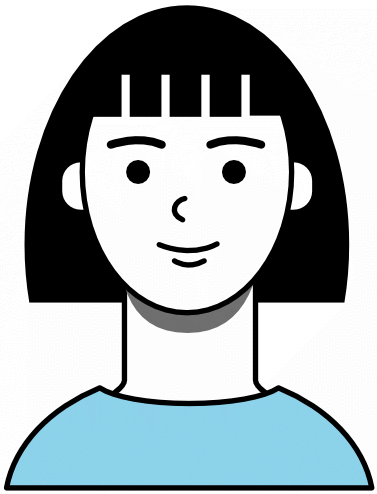
Comments