
奈良県明日香村にある「橘寺」。聖徳太子の生誕地と伝わり、聖徳太子が建立したとされる七大寺の一つです。
聖徳太子建立七大寺とは、法隆寺、広隆寺、法起寺、四天王寺、中宮寺、橘寺、葛木寺。
(葛木寺は唯一所在が確認されていません)

本堂
橘寺の創建由来の詳細は不明ですが、かつて欽明天皇の別宮・橘宮があった場所で、そこを散策中の穴穂部間人皇女が厩戸で出産したのが聖徳太子(厩戸皇子)とされています。
文献に橘寺が初めて登場するのは『日本書紀』天武天皇9年(680年)で、「橘寺尼房失火、以焚十房」(橘寺の尼房で火災があり、十房を焼いた)とあります。
橘寺の北側には川原寺が位置し、川原寺に対する尼寺として橘寺が建立されたとする説もあるようです。

本堂には聖徳太子35歳の像、聖徳太子坐像(重要文化財)が本尊として安置されています。
室町時代の永正12年(1515年)、椿井舜慶作。


伝日羅立像(重要文化財)
平安時代作・像高144.6cm、ヒノキ一木造
日羅(にちら)は百済出身の高僧で、聖徳太子の仏教の師であったと伝えられています。
伝日羅と「伝」の字がつけられているのは、この立像が日羅像なのか、地蔵菩薩像なのか、僧形神像なのか判別できないため。
橘寺といえば、こちらの伝日羅立像が有名です。貞観(じょうがん)彫刻の作例。
貞観彫刻とは、平安時代前期の貞観時代に制作された彫刻のこと。天平時代と藤原時代に挟まれた時代で、天平仏とも藤原仏とも異なった独特の特徴を持つ。
聖倉殿(収蔵庫)に安置されていますが、普段は非公開。春秋に期間限定で公開されます。

太子の生誕から薨去までを描いた「聖徳太子絵伝(重要文化財)」も必見です。全8幅。
室町時代に奈良で活躍した絵師・琳賢(りんけん)の周辺で描かれたと考えられています。
聖倉殿で毎年春と秋に2幅ずつ特別公開されます。係の方に説明してもらいながら観覧できたので、とっても面白く、もっと知りたくなったので、思わず帰りに「週刊 絵で知る日本史17 聖徳太子絵伝」を購入してしまいました。

二面石
飛鳥時代の石造物。右善面、左悪面と呼ばれ、人の心の二面性を表現しているそうです。
↑が左悪面で、↓が右善面でしょうか。


三光石
橘寺の境内に安置されている奇岩。聖徳太子が勝鬘経(しょうまんぎょう。大乗仏典の一つ)を講讃(経文の意味・内容を講義し、その功徳をたたえること)した際、日、月、星の光を放ったと伝えられています。

阿字池
梵字の「ア」を形取って聖徳太子が作られたと伝えられています。

往生院の天井画
1997年(平成9年)に建立。現代画家らによって260点の花の天井画が奉納されています。
橘寺の北側にある川原寺も一緒に訪れたので、また別記事に。川原寺は現在は跡地しか残っていません。
<橘寺>
【住所】奈良県高市郡明日香村橘532
【電話】0744-54-2026
【時間】9:00〜17:00
【拝観料】一般350円
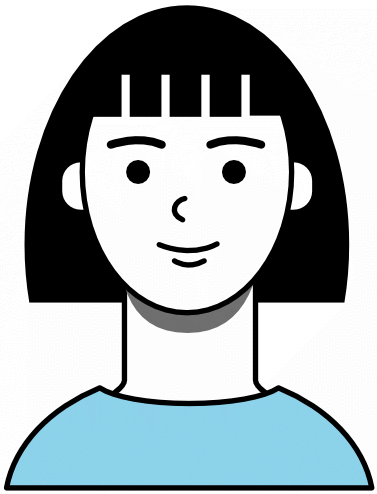
Comments