
石川県中能登町にある「山田寺(やまだじ)」。
北陸三十三ヵ所観音霊場の第二十番です。
山田寺は天平宝字元年(757)、泰澄大師によって開基されたと伝わり、古くから石動山や気多大社とは密接な関係を持ち、広大な寺領を有していました。
泰澄(たいちょう)大師
奈良時代の修験道の僧。
天武天皇11年(682)、越前(福井県)生まれ。
富士山、立山とあわせて日本三霊山に数えられる白山を開山した。
石動山(せきどうさん)
石川県と富山県の県境近くにある標高565mの山で、古来山岳信仰の霊場であった。
石動山に坊院を構えた天平寺は、天皇の御撫物の祈祷をした勅願所である。
最盛期の中世には北陸七カ国に勧進地をもち、院坊360余り、衆徒約3,000人の規模を誇ったと伝えられる。

本堂
建武2年(1336)に能登国司・中院定清(なかのいん さだきよ)は足利尊氏に味方して、石動山で越中守護・井上俊清を迎え撃ちましたが敗れ、七堂伽藍と十六坊を数えた当寺も石動山寺坊と共に焼失しました。
復興後も、天正10年(1582)に石動山衆徒に協力し、前田利家と戦って、再び焼失。
その後、正親町天皇の綸旨を奉じた利家によって復興されましたが、次第に衰退。
宝永2年(1705)に中興の僧・堯正和尚により本堂と観音厨子を再興しました。
文化9年(1812)に良遍和尚が境内に白山権現社を迎え、神輿も造られ盛況を呈しました。
現在は、こぢんまりとした本堂、鐘楼堂のみが残っています。

本堂内

御本尊は十一面観世音菩薩像で、行基の一刀三札の作であると伝えられています。
一刀三札とは、仏像を彫刻するときに一彫りごとに三度礼拝すること。



同じ境内にある白比古神社
白比古神社の主祭神は白比古大神。
能登地方の開発神・大己貴命(大国主命のこと)の御子神であることから、大己貴命を主祭神とする気多大社と関係が深いそうです。


御朱印
北陸三十三ヵ所観音霊場 第二十番
<白良山 山田寺>
【住所】石川県鹿島郡中能登町良川ト5甲
【電話】0767-74-0272
【宗派】真言宗
【拝観料】志納
【駐車場】あり
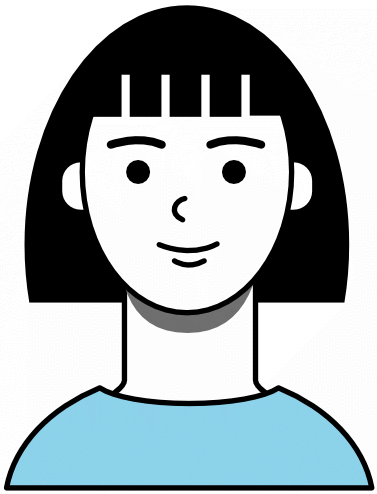
Comments